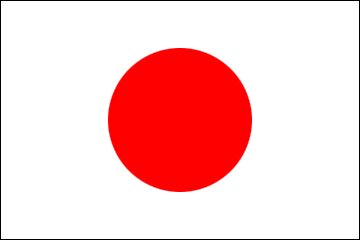カイロ大学主催シンポジウム 「非西欧社会の近代化再考:日本(東アジア)とエジプト(アラブ)の場合II」を開催
令和2年3月8日

2020年3月7日,能化正樹駐エジプト日本大使は,カイロ大学で開催された同大学文学部日本語日本文学科主催,日本研究シンポジウム「非西欧社会の近代化再考:日本(東アジア)とエジプト(アラブ)の場合II」に出席しました。
同シンポジウムは日本大使館,久留米大学,及び国際交流基金の協力により,3月7,8日に開催され,日本から招へいした中西進国際日本文化研究センター名誉教授,五百旗頭薫東京大学教授,田中克彦一橋大学名誉教授が,エジプト(アラブ)と極東日本の近代化再考をテーマに基調講演を行いました。
能化大使は,開会式で,本年大エジプト博物館が開館するピラミッド地域を150年以上前に訪れた日本の侍たちの記念写真が残っており,これが日本とエジプトの交流の原点になったことを紹介しました。大使は,「この侍たちはエジプトの前に立ち寄ったアジアと中東の港を西欧列強が支配していたことに衝撃を受けました。独立を守るためのこのような危機意識が日本の近代化の原動力になりました。今日,西欧社会も多くの問題を抱える中,改めて非西欧社会の国々がお互いの関係を見つめ直すことは大変意義深いと思います。」と述べました。
同シンポジウムは日本大使館,久留米大学,及び国際交流基金の協力により,3月7,8日に開催され,日本から招へいした中西進国際日本文化研究センター名誉教授,五百旗頭薫東京大学教授,田中克彦一橋大学名誉教授が,エジプト(アラブ)と極東日本の近代化再考をテーマに基調講演を行いました。
能化大使は,開会式で,本年大エジプト博物館が開館するピラミッド地域を150年以上前に訪れた日本の侍たちの記念写真が残っており,これが日本とエジプトの交流の原点になったことを紹介しました。大使は,「この侍たちはエジプトの前に立ち寄ったアジアと中東の港を西欧列強が支配していたことに衝撃を受けました。独立を守るためのこのような危機意識が日本の近代化の原動力になりました。今日,西欧社会も多くの問題を抱える中,改めて非西欧社会の国々がお互いの関係を見つめ直すことは大変意義深いと思います。」と述べました。


基調講演者の一人,中西教授が研究する「万葉集」は,7世紀から8世紀に編纂された日本最古の和歌集で,新しい天皇陛下の下で始まった時代「令和」の原典でもあります。中西教授は,日本が「開国」した明治以前から,近代化は始まっていた一方,真の近代化は第二次世界大戦が終了してからだ,とも説明しました。そして和歌の改革者でもある松尾芭蕉の言葉である「不易流行」,すなわち「変わらざるもののための流行」という概念を取り上げ,悠久でありながら常に流れているナイル川のようにエジプトの近代化が進むことを願うと講演を締めくくりました。


2日間に亘るシンポジウムでは,エジプトだけでなく,レバノン,イラク及びスーダンのアラブ諸国と日本から日本研究者が一堂に介し,エジプト(アラブ)・日本(東アジア)との近代化の比較研究や,思想,近現代文学,国語等の分野ごとに近代化を考察するセッション,さらには日本語教育に関するセッションが設けられ,極めて質の高い発表と議論が行われました。
本シンポジウムは,日本とアラブ諸国の日本研究者達の交流の場ともなり,研究者間のネットワークが強化されました。今後も,アラブ諸国における日本研究がますます発展し,日本とアラブ諸国の相互理解が促進され,協力関係が強化されるよう,期待します。
本シンポジウムは,日本とアラブ諸国の日本研究者達の交流の場ともなり,研究者間のネットワークが強化されました。今後も,アラブ諸国における日本研究がますます発展し,日本とアラブ諸国の相互理解が促進され,協力関係が強化されるよう,期待します。